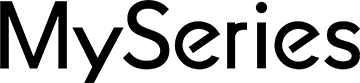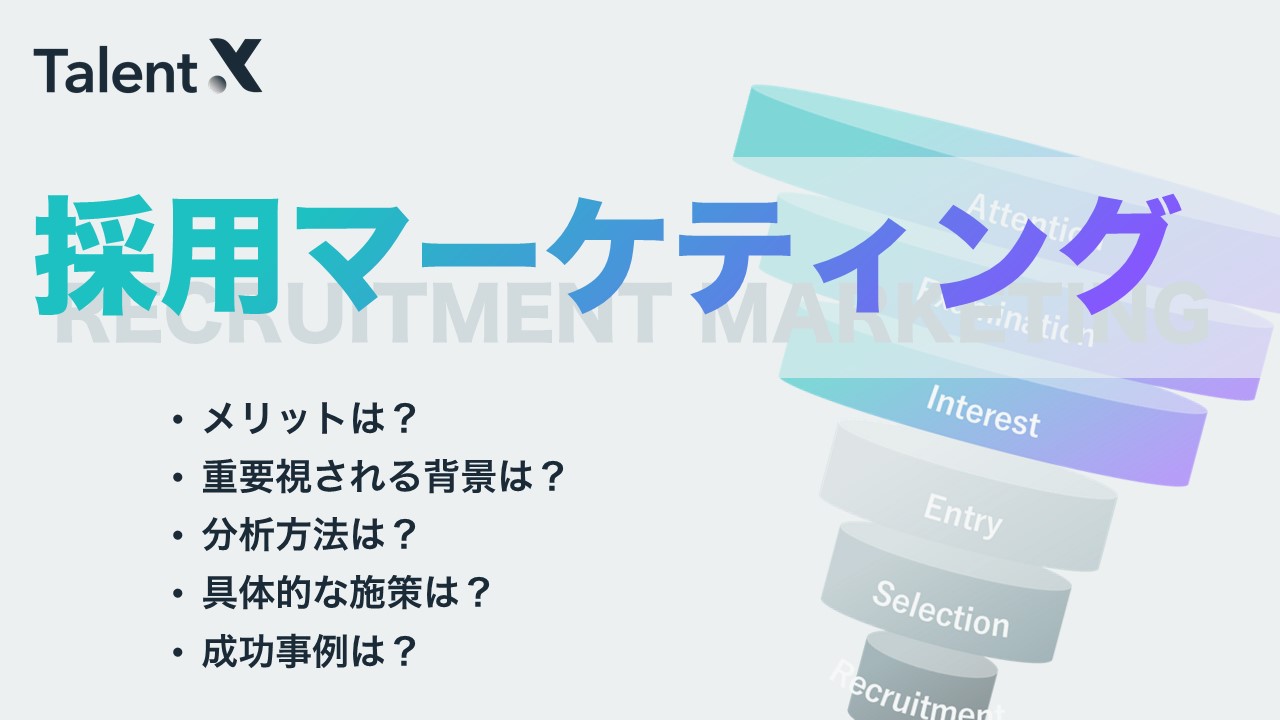近年ではポートフォリオという言葉を耳にする機会が多くなっています。
ポートフォリオ( Portfolio)は 、本来の意味としては「紙挟み」「書類かばん」などを指す言葉であり、その他にもクリエイターの作品集を指す場合もよく見られます。ポートフォリオという言葉は、上記以外にも使用される範囲が広まっており、金融・投資用語、教育用語、そして人事分野でも「人材ポートフォリオ」としてよく使われています。
人材ポートフォリオとは、自社内の人的資源がどのように構成されているのかといった現状を示す場合と、将来的にどのような人材が必要になるのかを示す場合の2つの視点で示されます。
この記事では、人事分野で使われている人材ポートフォリオについて、意味や作り方とポイント、メリットなどをわかりやすく解説します。
目次<人材ポートフォリオとは?意味や作り方・ポイントとメリットを解説 >
- 人材ポートフォリオとは
- 人材ポートフォリオが注目されている背景
- 人材ポートフォリオを作成する効果やメリット
- 人材ポートフォリオの作成の流れとポイント
- まとめ<人材ポートフォリオとは?意味や作り方・ポイントとメリットを解説>
人材ポートフォリオとは
人材ポートフォリオとは、企業が事業活動に必要な人材のタイプ(職種、能力、スキル、経験など)を明確にした上で、自社内の人的資源がどのように構成されているのか、あるいは必要となるのかを示したものです。
人材ポートフォリオをわかりやすく言い換えると、自社のどこの組織に、どのような経歴や能力を持つ人材が、どのくらい在籍しているのか、もしくは必要となるのかを表わしたものといえます。
人材ポートフォリオの2通りの考え方
人材ポートフォリオは、自社において人的資源がどのように構成されているのかという現在の状況を表わす場合と、事業成長に向けて推進して行く上で必要となる将来の人的資本の姿を示す2通りがあります。
どちらの人材ポートフォリオのケースでも、自社に必要となる人材のタイプを理解し、最適な人員配置を行い、不足が考えられる場合には育成や採用によって充足させていく必要があるといえます。
人材ポートフォリオが注目されている背景
人材ポートフォリオが注目されている背景には、ISO30414の影響から人的資本開示の要請が高まっていることがあげられます。
また、人材ポートフォリオが必要とされる理由はいくつか知られていますが、ここでは企業側の視点から代表的な3つの理由をご紹介します。
- 労働力人口の減少や専門人材不足
- 働き方や雇用形態の多様化
- 自社をとりまくビジネス環境の変化
労働力人口の減少や専門人材不足
少子高齢化による労働人口の減少やITエンジニアなどのような専門性の高い人材の慢性的な不足により、多くの企業が人手不足の状態となっています。このような労働力不足を補うために、人材ポートフォリオリによって適材適所の人員配置を可能にしたり、将来必要となる人材を可視化し育成や採用にも活用できるので各企業は注目しています。
働き方や雇用形態の多様化
企業で働く従業員の働き方や雇用形態の多様化が急速に進んでいることも、人材ポートフォリオが注目されている理由の1つです。オフィスで働くことに加えて、テレワークで働くケース、また両方を組み合わせて働くハイブリッドワークのように、働く場所も多様です。また、勤務時間や雇用形態についても、フレックスタイム、時短勤務、副業など様々な形で働く従業員が増えています。
このように多様な働き方に対応していくためには、人材ポートフォリオによって自社の労働力の実態を認識し、最適な配置を目指す必要が求められている点も注目されている理由です。
ハイブリッドワークとは?テレワークとの違いやメリット・デメリットを解説
自社をとりまくビジネス環境の変化
DX、グローバル化、また世界情勢など企業を取り巻くビジネス環境の変化が絶えず起きています。VUCA時代とも呼ばれている、このような目まぐるしい環境の変化を乗り越えて、ビジネスの成長を推進するとともに、イノベーションを創出するといった観点からも人的資源を最適に組み合わせていく人材ポートフォリオが求められています。
VUCAとは?予測不能なVUCA時代の企業に求められる組織づくりと採用戦略
人材ポートフォリオを作成する効果やメリット
人材ポートフォリオを作成することによって、どこの組織に(部署、部門、役職、ポジションなど)、どのような人材が(職種、スキル、能力、適性)、どのくらい(人数、在籍年数)いるのかが可視化されます。それによって得られる代表的な効果やメリットを3点ご紹介します。
- 自社の人材が可視化され適材適所の人材配置ができる
- 人材の過不足の把握と人件費の削減につながる
- 従業員一人ひとりに合わせたキャリア支援ができる
自社の人材が可視化され適材適所の人材配置ができる
人材ポートフォリオによって各組織に所属する個々の従業員の職種、スキル、能力、適性などが明確になり、その本人の能力が適切に発揮できているのかが可視化されます。また、各部署にどのような人材がいるのかといったことも明確になります。人材ポートフォリオに基づいて部門間の異動などを行い、適材適所の人材配置が可能になります。
人材の過不足の把握と人件費の削減につながる
人材ポートフォリオによって、どこの組織にどのくらいの人材がいるのかが明確になり、各組織のミッションや規模・範囲などに対して適切か否かの判断が可能になります。人材のスキルやキャリア、人員の過不足などを正確に把握することで、適正な人員配置につながり無駄な人件費の削減につながっていきます。
従業員一人ひとりに合わせたキャリア支援ができる
人材ポートフォリオによって、個々の従業員が持つスキル、能力、経験、適正などを把握することによって、それぞれに合ったキャリア支援が可能になります。 既に持っているスキルや能力を最大限に発揮できる職種やポジションへの異動、自社の事業戦略から将来的に身につけたほうがベターといえるスキルの教育や育成など従業員の志向性にマッチしたキャリアパスの提示などさまざまな形でキャリア支援を行うことが可能です。
人材ポートフォリオの作成の流れとポイント
人材ポートフォリオを作成する際の流れと注意すべきポイントを段階に沿ってご紹介します。
- 自社の事業計画や方向性を明確化する
- 自社に必要な人材や職種のタイプを定義し人員数を分析する
- 定義した人材や職種のタイプを、現在の組織や従業員に当てはめる
- 人材の過不足を確認し、抽出した課題の解決策を検討する
1.自社の事業計画や方向性を明確化する
人材ポートフォリオを作成する最初の段階で、自社の事業計画や方向性を明確にし、作成にかかわる関係者の共通認識をとります。それを前提とした人材ポートフォリオを作成することによって、必要となる人材の最適配置が実現されます。
2.自社に必要な人材や職種のタイプを定義し人員数を分析する
共通認識となった自社の事業計画や方向性を基準として、必要な人材のタイプや人員数を分析していきます。 人材のタイプの分類には、業務の性質での分類、仕事のスタイルや考え方による分類、志向と得意分野による分類、雇用形態による分類など多様な観点が知られています。自社の事業計画や方向性にマッチした分類方法を採用することは重要なポイントです。
3.定義した人材や職種のタイプを、現在の組織や従業員に当てはめる
定義した自社に必要な人材や職種のタイプを、自社の組織や従業員に当てはめます。その際には、各組織の現状と個々の従業員が持つ労力やタイプの両面の観点から当てはめることが重要です。それによって理想と現実のギャップが見えてきます。
4.人材の過不足を確認し、抽出した課題の解決策を検討する
可視化された人材の過不足を確認し、その課題を抽出します。抽出した課題を解消して、あるべき姿とのギャップを埋めるための解決策を推進します。
短期的には、人材の異動による適材適所を図ります。また、自社内に対応する人材がいない場合には、教育やトレーニングを積むことによる育成をしたり、すでに必要な能力やスキルを持った人材を採用することによって充足させることができます。各企業の事業計画や方向性にマッチした解決策を検討し推進することがポイントです。
まとめ<人材ポートフォリオとは?意味や作り方・ポイントとメリットを解説>
自社の事業計画や方向性を基準として、自社に必要な人材のタイプや人員数などを明確にする人材ポートフォリオを作成することは、企業の事業成長にとって欠くことの出来ない重要なことといえるでしょう。
労働人口の減少や求人倍率が上昇する採用難の状況においては、個々の従業員のタイプを理解し、最適な人員配置を行い、人材不足が考えられる場合には育成や採用によって充足させていくことが必要になっています。
TalentXでは、様々な採用課題の解決を支援するサービスを提供しています。採用マーケティング、リファラル採用、採用ブランディングなどトータルでご支援させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
・国内初の採用MAサービス「Mytalent」
・リファラル採用サービス「MyRefer」
・採用ブランディングサービス「MyBrand」
監修者情報
監修 | TalentX Lab.編集部
この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。