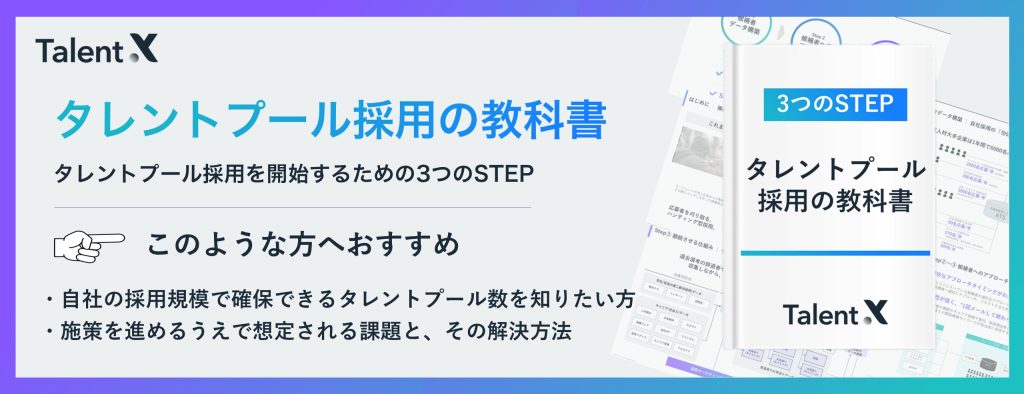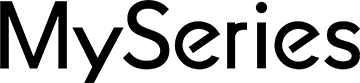地域経済の活性化を担う地方銀行にとって、安定的な人材確保は恒久的な課題です。そんな中、株式会社名古屋銀行様(以下、名古屋銀行)は、「MyTalent」を通じてアルムナイや新卒内定辞退者との繋がりを維持、強化する「タレントプール採用」を導入しています。
名古屋に根差した銀行ならではの「人の繋がり」を資産とし、いかにして採用力向上に繋げ、ひいては地域や業界の活性化にも貢献していくのか、その取り組みの裏側を伺いました。

株式会社名古屋銀行
・従業員 :1,786名
・事業 :銀行業務、リース業務、カード業務など
・取材対象者:常務執行役員 人材開発部長 鈴木 克典 氏
人材開発部 人事グループ副業務役 貝瀬 繭子 氏
人材開発部 採用教育グループ 馬場 歩美 氏
人材開発部 採用教育グループ 中嶋 歩佳 氏
「未来創造業」を掲げ地域とともに歩むために―求めるのは、地域貢献への想いがある多様な人材
貴行の事業内容と求める人物像についてお聞かせください。
中嶋氏:
当行は銀行業の枠組みを超えて、お客様の未来に繋がる仕事を創造していく「未来創造業」を掲げています。これまでの預金融資の相談だけでなく、どんなことでも当行に相談すれば解決する、そんな存在を目指しています。幅広い領域でお客様へのご支援を行うため、新卒採用に関しては多様なバックグラウンドを持つ方を求めています。
鈴木氏:
キャリア採用についても同様ではありますが、各募集職種に求められるスキルはもちろんのこと、この地域に根を張って活躍したい、これまでのキャリアで培ったスキルや経験を当行で発揮し地域貢献したい、という想いのある方に来ていただきたいです。
地域に愛着を持つ人々が多い名古屋の特性を生かし、「いつでも帰ってこられる場所」でありたい―アルムナイ採用の体系化が「MyTalent」導入のきっかけ
昨年度からキャリア採用の目標が1.5倍に増えたと伺いました。その中で、アルムナイ採用やタレントプール採用という新しいアプローチに目を向けられたきっかけは何でしたか。
鈴木氏:
当行はダイバーシティ推進という観点で、多様なバックグラウンドを持つ方々が活躍できる職場環境にするために、キャリア採用目標を1.5倍に増やしました。目標の増加に伴いアルムナイ採用等にも注力していきたいと思っていた一方、退職者との連絡手段が整備されておらず、人事から直接アプローチする手段に限りがありました。
加えて、当行が拠点を置く名古屋という土地柄、地域への思い入れが強い方が多く、たとえ退職されても同じ地域で活躍されていたり、同僚と繋がっている方が多いという特性がありました。そうした方々に対して、辞めたから当行と無関係になるのではなく、「いつでも帰ってこられる場所として長くお付き合いしていきたい」という想いが根底にありました。
人と人との繋がりを、人事としても公式に把握し体系化したいと考え、「MyTalent」の導入に至りました。
内定を辞退された方との関係構築にも関心を持たれたそうですね。
鈴木氏:
新卒選考は当行を研究して応募いただく方も多く、内定という縁のあった方々ですので、もし状況が変わって当行で働きたいと思ったときに、再びその機会を提供するのは重要なことだと考えています。また、昨今多くの企業がこうした取り組みを始めている外的要因も考慮し、新卒内定辞退者への関係構築も早急に進めたいと考えました。

「MyTalent」によって退職者や内定辞退者の行動を可視化、施策の工夫や振り返りにも効果的
「MyTalent」を導入し、どのような効果を感じていますか。
中嶋氏:
「MyTalent」では主に退職者と新卒内定辞退者へのアプローチをしていますが、これまでの採用媒体ではできなかったメールマガジンの開封率やURLのクリック率まで細かく把握できる点が大きなメリットです。これにより、候補者の興味や関心が可視化されました。特に、新卒内定辞退者は「働き方」に関する情報への関心が高いことが分かり、メルマガの内容を工夫する上で非常に役立っています。
鈴木氏:
メールの開封率やクリック率が可視化できたことで、退職者が意外と当行の情報を気にかけてくれていることも実感しました。また、復職を希望する方が思ったよりも早く現れたのも嬉しい発見でした。他社に転職したうえで、「名古屋銀行の方が自分に合っていたかも」という声を聞くと、カムバックできる環境を用意しておくことの大切さを実感します。

「MyTalent」を活用したアプローチで工夫されている点はありますか。
馬場氏:
内定辞退者に対しては 「もう一度選考を受けてほしい」と強く迫るのではなく、「情報発信を続けるので、よければ見てください」「もしカジュアル面談に興味があれば返信してください」といった、相手に負担を感じさせないスタンスを心がけており、連絡頻度も月に1回程度に留めています。
貝瀬氏:
退職者の方々には、育児・介護との両立支援制度などの新しい取り組みを通じて、働き方が在籍当時と大きく変化している点を重点的に発信しています。当行の直近の離職率は3.6%で、これは全国平均の15.4%と比較してもかなり低く、客観的な「働きやすさ」を伝えることも重要だと考えています。 さらに、現役行員に協力を仰ぎ、退職した同僚に連絡してもらうキャンペーンも実施しました。組織全体を巻き込んで実施したところ、当行独自のアルムナイコミュニティである「ジョインネットワーク」への登録者数が一気に増え、若い世代よりも中年層の方々から多くの反応がありました。

最後に、今後のタレントプール採用における展望をお聞かせください。
鈴木氏:
当行では、人との「ご縁」を大切にし、退職された方や選考を辞退された方とも長く繋がり続けていきたいと考えています。その想いを体系化してくれる「MyTalent」は、我々にとってなくてはならない存在です。他社で活躍されている方が、そのスキルを持って当行に戻ってきてくれる際の橋渡し役として、今後も「MyTalent」には大いに期待しています。
貝瀬氏:
「MyTalent」導入当初から、採用の向上だけでなく、一度当行と縁があった方々との交流を通じた地域の活性化を大きなゴールとして掲げています。タレントプールは企業同士が人材を奪い合うシステムではなく、「繋がり」の創出によってお互いを高め合っていくきっかけにもなりうると確信しています。
中嶋氏:
今後もタレントプール登録者と定期的な連絡を通じて繋がりを保ち、当行のことを思い出してもらう機会を失わないようにしたいです。たとえ入行に至らなくても、何らかの形で関係が続くことが大切だと考えています。
馬場氏:
企業同士の情報交換の場としてもこの繋がりを活かせれば嬉しいです。まずは、新卒内定辞退者の中から数名でも「やっぱり名古屋銀行は良かった」と思ってもらえるような事例をつくっていきたいです。
編集後記
地域に根差し、人と人との繋がりを何よりの資本としてきた地方銀行にとって、タレントプールという仕組みは、その強みを最大限に活かすことのできる重要な存在ということがうかがえるインタビューでした。属人的なネットワークに頼っていたアルムナイ採用をデータとして可視化し、戦略的にアプローチすることで、採用だけでなく新たなビジネスチャンスの創出や、ひいては地域全体の活性化にまで繋がる可能性を秘めています。
採用候補者との中長期的な関係構築手法や、採用候補者ごとにカスタマイズしたアプローチに関心のある採用担当者様は、ぜひTalentXまでお問い合わせください。
▼タレントプールによる転職潜在層へのアプローチなど、多様な人材確保に向けた戦略的な採用活動を進める、ほくほくフィナンシャルグループ様のお取組みはこちらから
記事URLはこちら:https://mytalent.jp/lab/case_hokuhoku-fg
▼タレントプールとは何か、タレントプール採用を導入するために何から始めればいいか気になる方は、以下の「タレントプール採用の教科書」も併せてご覧ください。