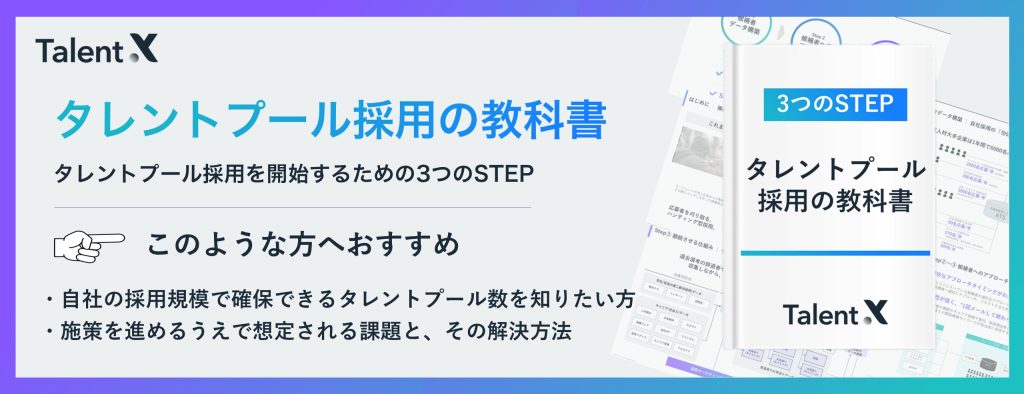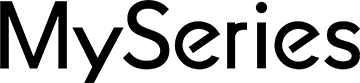名古屋市で医療・介護・保育施設を運営する医療法人としわ会様(以下、としわ会)は、採用競争が激化する介護業界において、安定した「母集団形成」による持続可能な採用の実現を目指しています。そのなかで、採用MAサービス「MyTalent」によってタレントプール採用を導入し、介護業界では珍しい「キャリア登録」採用を開始。導入から14か月で14名の採用に成功し、採用コストを従来の約3分の1に抑えることができました。
本記事では、どのようにして「キャリア登録」が採用成果に繋がったのか、そして法人全体で採用活動に取り組むことの重要性について、法人本部 総務課 課長の安達 匡倫氏にお話を伺いました。

医療法人としわ会
・従業員数 :359名
・事業概要 :医療・介護・保育の施設運営
・取材対象者:法人本部 総務課 課長 安達 匡倫氏
安定した採用活動の実現に向けて、タレントプール登録者の動きが可視化できる「MyTalent」の導入を決意
貴法人の採用方針や求める人物像について教えてください。
安達氏:
主に欠員補充と、サービスの質向上に向けた増員を目的に採用を行っています。専門職において資格や経験が必要だということは言うまでもありませんが、それよりも、利用者様へのコミュニケーション能力やホスピタリティのある方かどうかが重要です。そのため、採用面接では第一印象や話し方、最低限必要なマナーを注視しています。
入職後もこの分野の教育には力を入れており、例えば、外国籍の職員が増加傾向にある中でどういった心構えや配慮が必要なのかを学ぶ研修を独自で取り入れています。
これまで取り組んできた採用手法と、その中で感じた課題を教えてください。
安達氏:
人材紹介はほとんど利用しておらず、求人広告やホームページのコンテンツ配信、Facebookなどによって、当法人の魅力を伝える機会を拡充させています。また、リファラル採用にも注力しています。
そんな中で、当法人の採用における一番の課題については「母集団形成」だと思っています。どの採用手法も、ある程度採用候補者を集められる一方で、どれかに偏っていると、いずれ応募数が鈍化することも感じていましたし、安定した採用活動の実現にはずっと同じやり方で進めるのではなく、採用手法に加え情報の出し方も都度工夫していく必要があると痛感しました。
その中で、「MyTalent」を導入した背景を教えてください。
安達氏:
もともとリファラル採用サービス「MyRefer」を利用しており、TalentXさんの担当から勧められたのがきっかけでした。以前から「タレントプール採用」の存在自体は耳にしていましたし、過去の採用活動で接点を持った方々へのアプローチは独自でやっていました。しかしながら、工数がかかることに加え、1年以上前の採用候補者との会話記録の残しにくさや対応の属人化が課題となり、なかなか採用成果に結び付くことがありませんでした。
その中で「MyTalent」は、登録者の動きを可視化できデータを蓄積できる点が魅力だと感じ、導入を決めました。特に上層部での稟議において決め手になった点が、「トラッキング機能」で採用候補者が採用サイトを閲覧した動きを把握できるのは、通常の採用活動の改善にも役立つと感じています。
採用候補者の状況に応じた導線を増やすことで、「MyTalent」導入14か月後にはタレントプール経由で14名の採用が決定

「MyTalent」によってタレントプール採用を始めてから、成果や効果を感じたきっかけは何でしたか?
安達氏:
求人案内を希望する方への登録導線を、採用ホームページに設置する「キャリア登録(求人案内登録フォーム)」を始めたことでした。この手法は介護業界でも珍しく、当初は「当法人に興味があるのであれば、応募をしてくるものではないか?」と懐疑的な印象を抱いていましたが、TalentXさんのご提案もあり始めました。すると、「MyTalent」導入後14か月で14名の採用に繋げることができました。またタレントプール採用によって、従来の採用手法に比べ、コストを約3分の1に抑えることができ、今では「キャリア登録」の効果を大いに実感しています。
▼入社者インタビュー:医療法人としわ会のタレントプール採用~「キャリア登録」によって安心して踏み出せた新たなキャリア~
https://mytalent.jp/lab/case_toshiwa-kai3/

「キャリア登録」の取り組みを経て、何か気づきや学びがあれば教えてください。
安達氏:
「キャリア登録」経由の登録者の中には、さまざまな状況の方がいることがわかりました。当法人への志望度が高い方もいれば、まずは施設見学がしたい方、今すぐではなくて1年後2年後に転職したい方、ただ情報収集をしたいだけという方もいます。登録者それぞれに転職状況や当社への関心度があり、個別最適化した導線設計やコンテンツ配信が必要だと再認識しました。
人材紹介や求人広告の場合は複数法人と比較検討している候補者が多いですが、「キャリア登録」の場合、登録者の転職意向によっては併願していない方も多く、双方のミスマッチ軽減ができればご入職いただける確率が高いと感じています。これは現場で面接する施設管理者からも同様の声があり、母集団形成だけでなく採用の質向上にも繋がりました。
法人全体で「採用」と向き合わなければいけない介護業界の今、タレントプール採用を法人全体で取り組む手法として変革させていきたい
採用候補者を取り巻く状況が目まぐるしく変化している中、介護業界では今後どのようなニーズや動向がでてくると思いますか?
安達氏:
介護職の最新のトレンドとして、業界全体の離職率は現在約12% ※1と年々改善傾向にある一方、採用率は低下傾向にあり、採用ハードルは今後も高まっていくとされています。どの職場でも働きやすい環境になりつつある中で、求人条件や働くことによる付加価値などがこれまで以上に求められ、総括的に選ばれる状態を作らなければなりません。それを踏まえると、採用課題は採用部門だけで解決するのではなく、働き方改革や組織経営を通じて法人全体で向き合うべき課題だと考えています。
※1 公益財団法人介護労働安定センター:「令和6年度「介護労働実態調査」より
法人全体で「働くこと」や「採用」について考えていく必要がある中、貴法人では本部と施設との連携をどのように進めていますか?
安達氏:
企業様によっては、採用を本部が一括管理している場合と、現場責任者に委任している場合に分かれると思います。個人的には、どちらかに寄りすぎることなく、バランスを保つことが重要だと考えています。採用面接は原則各施設でやってはいるものの、採用候補者が求めている働き方や労働条件の交渉は本部と行った方が良いケースもありますし、反対に、現場特有の空気感やカルチャーに関することは現場でしかわかりません。現場と本部がお互いの状況を共有し合い、各々の立場でベストを尽くすことで、法人全体としてより良い価値を採用候補者に提供できるのではないでしょうか。
「タレントプール採用」を検討中の法人様に、伝えたいことはありますか?
安達氏:
タレントプール採用の導入当初、現場の採用担当者が手法を理解するのが困難なこともありました。しかし採用成果が見えるにつれて、タレントプール経由での応募は良い方が多いという良いイメージに繋がり、さらに採用効果が促進されているように感じます。
先ほどご説明した「キャリア登録」などの新たな採用手法は成功事例も少なく、まずはやってみないとわからないという言葉に尽きることも事実です。そのため、タレントプール採用を導入するうえで何よりも大切なのは、採用担当者の採用に対する考え方や捉え方ではないでしょうか。
人材紹介や求人広告など、外部採用を利用することは必ずしも悪いことではないと思います。成功報酬型のサービスであれば、採用成果と掛かったコストが見合いますし、安心性はあります。しかし、外部採用に依存すると採用に対して消極的になってしまい、新たな採用手法が台頭しても一歩踏み出しづらくなってしまうと思います。
「自分たちの力で採用する」という強い決意をもったうえで、様々な採用手法をバランスよくやっていくことで、人材紹介や求人広告を使わないと採用できない依存状態から脱却できると思います。今後も介護業界の皆さんと手を取り合い、より良い採用市場をつくっていきたいと思います。最後に、貴法人の今後の展望についてお聞かせください。安達氏:
「MyTalent」においては、母集団形成という観点でプール数の増加に今後も取り組んでまいります。加えて、先ほど申し上げたように採用の難易度はさらに厳しくなっていく中で、当法人に合う方と多く出会えるよう、様々な採用手法・ツールを活用していきたいと思います。
編集後記
「タレントプール採用」といった新たな採用手法の導入において、単に手法を取り入れるだけではなく採用担当者自身のマインドセットがいかに重要であるかを再認識しました。また、採用競争が激化する介護業界において、「自分たちの力で採用する」という信念のもと、選ばれる企業になるために法人全体で働きかける必要があることが伝わるインタビューでした。
採用候補者との中長期的な関係構築手法や、採用候補者毎にカスタマイズしたアプローチに関心のある採用担当者様は、ぜひTalentXまでお声がけください。
▼タレントプールで介護業界の「人財供給力」を高める、ニチイ学館様のお取組みはこちらから
記事URLはこちら:https://mytalent.jp/lab/case_nichiigakkan/
▼タレントプールとは何か、タレントプール採用を導入するために何から始めればいいか気になる方は、以下の「タレントプール採用の教科書」も併せてご覧ください